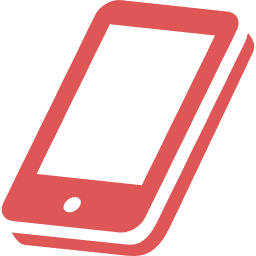箱根の雄大な自然に抱かれた別荘、熱海の夜景を一望できるマンションの一室。これらの素晴らしい物件を手に入れ、「さあ、これから民泊事業を始めるぞ」と夢と希望に胸を膨らませているオーナー様。その一歩、本当に大丈夫でしょうか。
「物件さえあれば、Airbnbに登録すればすぐにでも始められる」。そんな風に考えているとしたら、それは非常に危険なサインです。民泊事業は、あなたが思っている以上に、多くの法律や条例によって厳しく規制されています。そして、その中でも最も根幹にあり、物件購入や賃貸契約を結んだ後では取り返しがつかない要素が「用途地域」です。
「用途地域って何?」「なんだか難しそう…」。そう思われる気持ちはよく分かります。しかし、この知識なくして民泊事業に乗り出すのは、羅針盤を持たずに大海原へ漕ぎ出すようなものです。最悪の場合、多額の投資をしたにも関わらず、一日も営業できずに撤退を余儀なくされる可能性さえあります。
この記事では、難解に聞こえる「用途地域」というルールを、民泊オーナー様の視点から徹底的にかみ砕いて解説します。さらに、神奈川県(箱根・小田原)と静岡県(熱海・伊東)の各自治体が独自に定める「上乗せ条例」という、このエリアで事業を行う上で絶対に知らなければならないローカルルールの現実にも深く切り込みます。法令遵守は、単なる義務ではありません。それは、あなたの事業をリスクから守り、地域住民に応援されながら持続的に成長するための、最も重要な「経営戦略」なのです。
全ての基本、「用途地域」とは何か?~土地の性格を知る~
用途地域とは、一言でいえば、都市計画法に基づいて定められた「土地利用に関する基本的なルール」です。それぞれの土地に「ここは静かな住宅街にしましょう」「ここは商業施設を集めて賑やかな場所にしましょう」といった形で、13種類の「性格」が割り当てられています。この性格付けによって、私たちは無秩序な開発から守られ、快適な都市生活を送ることができています。
なぜ土地に「性格」を決める必要があるのか?
少し想像してみてください。もし、用途地域というルールがなかったらどうなるでしょうか。あなたが静かな暮らしを求めて建てたマイホームの隣に、ある日突然、深夜まで営業する工場や、大音量の音楽が流れる商業施設が建つかもしれません。これでは、安心して生活することができません。
そうした混乱を防ぎ、それぞれの地域が持つ機能を最大限に発揮できるよう、土地の使い道を大まかにゾーニング(区分け)しているのが用途地域です。民泊事業も、この土地利用の大きなルールの中に位置づけられているため、無視することは絶対にできません。
13種類の用途地域、その個性を理解する
用途地域は大きく「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分類され、さらに細かく13種類に分かれています。全てを暗記する必要はありませんが、民泊事業に関係の深い地域の「個性」を理解しておくことは、物件選びの際に非常に役立ちます。
例えば、「第一種低層住居専用地域」は、最も厳しく高さなどが制限された、いわば”お屋敷町”のようなエリアです。静かな環境が何よりも優先されるため、原則として店舗や事務所は建てられません。一方で、「商業地域」は、デパートや映画館などが集まる、いわゆる”繁華街”です。ここでは、日夜を問わず活気があることが求められます。
民泊施設は、この13種類の地域の「性格」と、これから解説する事業の法律が、どのように関わり合っているのかを理解することが、成功への第一歩となります。
「民泊新法」と「旅館業法」、あなたの事業モデルはどちら?
民泊を運営するには、主に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」と「旅館業法」という2つの法律が関わってきます。どちらの許可(あるいは届出)を取得するかによって、運営スタイル、収益性、そして用途地域との関わり方が大きく変わります。ご自身の事業モデルに合わせて、どちらが最適かを見極める必要があります。
手軽に始められる「民泊新法(住宅宿泊事業)」
2018年に施行された民泊新法は、既存の住宅を活用して、比較的簡易な手続きで宿泊サービスを提供できるようにした法律です。多くの「副業型」や「自宅活用型」の民泊は、この法律に基づいて運営されています。
最大のメリットは、その手軽さです。旅館業法のような厳格な設備基準(フロントの設置など)は求められず、「届出」という形で事業をスタートできます。用途地域との関係で言えば、原則として「人が住んでいる(または住むことができる)住宅」がある場所であれば、ほとんどの地域で運営が可能です。これは、物件探しの選択肢が広がるという点で、大きな利点と言えるでしょう。
しかし、大きな制約もあります。それは、年間営業日数が180日以内に制限されるという点です。つまり、一年間の半分は施設を稼働させることができません。このため、民泊事業を収益の柱としたい本格的な事業者にとっては、収益性に限界があるモデルと言えます。
本格的な事業展開が可能な「旅館業法(簡易宿所)」
一方で、旅館業法に基づく「簡易宿所」の許可を取得すれば、年間営業日数の制限なく、365日施設を稼働させることが可能です。本格的に民泊事業を展開し、収益を最大化したいのであれば、こちらの選択肢が視野に入ってきます。
しかし、その分、ハードルは高くなります。玄関帳場(フロント)の設置義務や、消防法令への厳格な適合など、求められる設備基準は民泊新法よりも厳しくなります。そして、用途地域に関しても大きな制約を受けます。旅館業の営業が可能なのは、原則として住居専用地域(第一種・第二種低層、第一種・第二種中高層)では認められていません。ホテルや旅館が建てられる地域に限られるため、物件探しの難易度は格段に上がります。
【最重要】箱根・熱海エリアで絶対に知るべき「上乗せ条例」の現実
さて、ここからが本題です。民泊新法は、「年間180日以内なら、住宅がある場所で広く民泊を認める」という国の大きな枠組みです。しかし、法律には「地域の事情に応じて、自治体がさらに厳しいルールを条例で定めることができる」という余地が残されています。これが、通称「上乗せ条例」と呼ばれるものです。
観光地でありながら、同時に多くの人々が静かな暮らしを営む箱根・熱海エリアでは、この上乗せ条例が民泊事業の行方を大きく左右します。国の法律だけを見て物件を決めてしまうと、思わぬ「待った」がかかるのです。
箱根町:「静寂」を守るための平日営業制限が意味するもの
豊かな自然と静かな環境を求めて多くの人が訪れる箱根町。この町の条例は、その「静寂」を守ることを強く意識しています。具体的には、住居専用地域(第一種・第二種低層、第一種・第二種中高層)において、民泊新法に基づく民泊の営業を「週末等(金曜日の正午から月曜日の正午まで)に限定する」という厳しい制限を設けています。
これは、何を意味するのでしょうか。年間180日という上限の中で、さらに平日の営業ができないということです。収益シミュレーションは大きく変わります。このエリアで民泊新法での運営を目指すのであれば、単価の安い平日を捨て、週末の宿泊単価をいかに最大化するかという、高度な運営戦略が求められます。また、平日の利用が見込めないため、清掃やメンテナンスのスケジュールは組みやすいという側面もありますが、収益機会が限定されるという事実は、事業計画の根幹に関わる重要な要素です。
熱海市:「駆けつけ義務」が問う、管理・清掃会社の真価
首都圏からのアクセスが良く、遠隔オーナーが多い熱海市。市の条例は、この「遠隔管理」という現実に即した、非常に重要なルールを定めています。それは、住居専用地域で民泊を運営する場合、住宅宿泊管理業者(管理会社)の営業所が、施設から車で30分(直線距離10km)以内に存在しなければならない、というものです。
この条例の背景には、過去に発生した騒音やゴミ出しといったトラブルがあります。問題が発生した際に、オーナーや管理者がすぐに現場に駆けつけ、対応できる体制を義務付けているのです。これは、遠隔オーナーにとって極めて重要なポイントです。つまり、「どの管理・清掃会社でも良いわけではない」ということを意味します。東京に本社があるだけの全国チェーンの業者では、この条件を満たせない可能性があります。
深夜の騒音トラブル、ゴミの不法投棄、急な設備不良。こうした事態に迅速に対応できるのは、熱海の地理と事情を熟知した、地域に根差した業者だけです。この条例は、清掃・管理会社の「地域密着度」と「緊急対応能力」を測る、一つのリトマス試験紙と言えるでしょう。
湯河原町・小田原市・伊東市:規制が緩やかだからこそ問われる「運営の質」
一方で、同じ観光地でも、湯河原町や小田原市、伊東市などでは、現時点(2025年10月)で箱根町や熱海市ほど厳しい上乗せ条例は施行されていません。しかし、これを「自由にできる」と考えるのは早計です。
規制が緩やかであるということは、それだけ運営者の自主的なモラルと、高い管理品質が求められるということを意味します。もし、一部の運営者がルールを無視した運営を行い、近隣トラブルが多発するような事態になれば、いずれは行政が厳しい規制に乗り出さざるを得ません。規制がないエリアで事業を行うことは、その地域の民泊全体の未来を左右する責任を負うことでもあるのです。
だからこそ、規制の有無に関わらず、騒音やゴミ問題を防ぐための徹底したハウスルールの周知、そして、それを担保する高品質な清掃・管理体制の構築が不可欠です。特に清掃は、施設の美観を保つだけでなく、チェックアウト後のゴミの適切な処理や、忘れ物の管理、設備の異常チェックといった、管理業務の最前線でもあります。ここに信頼できるパートナーを持つことが、持続可能な運営の鍵となります。
失敗しない物件選びのための、用途地域の具体的な調査方法
では、検討している物件の用途地域や、関連する条例を具体的に調べるには、どうすれば良いのでしょうか。3つのステップで、確実な調査方法を解説します。
ステップ1:インターネットで一次情報を確認する
まずは、物件の住所がわかっていれば、インターネットで手軽に調べることができます。「〇〇市 用途地域」といったキーワードで検索すれば、多くの自治体が用途地域マップ(都市計画図)をウェブサイトで公開しています。これにより、検討中の物件がどの色のエリアに属しているのかを、大まかに把握することができます。
ステップ2:自治体の窓口で最終確認を取る
インターネットの情報はあくまで参考です。最終的な判断を下す前には、必ず市役所や町役場の都市計画課などの担当窓口に直接出向き、正確な情報を確認しましょう。その際には、物件の住所がわかる資料(地図や公図など)を持参し、「この場所で、住宅宿泊事業法(または旅館業法)に基づく民泊は可能ですか?」「何か地域独自の条例や規制はありますか?」と、具体的に質問することが重要です。ここで、担当者から直接説明を受けることで、ウェブサイトだけでは分からなかった細かなニュアンスや注意点を把握できます。
ステップ3:不動産会社・専門家への確認でリスクを回避する
物件の売買や賃貸契約を進める際には、担当の不動産会社にも、その物件で民泊事業が可能であるかを確認する義務があります。しかし、不動産会社の担当者が必ずしも民泊の法令に精通しているとは限りません。最終的には、民泊事業に詳しい行政書士や、地域の事情に精通した清掃・管理会社など、複数の専門家の目でチェックしてもらうことで、リスクを最小限に抑えることができます。
まとめ
民泊事業を始めることは、空き家問題の解決や地域経済の活性化に貢献する、社会的にも意義のある活動です。しかし、その事業が、地域に暮らす人々の平穏を脅かすものであってはなりません。用途地域や上乗せ条例といったルールは、その共存のために設けられた、最低限の約束事です。
法令遵守は、事業をリスクから守るための「守り」の姿勢であると同時に、ゲストと地域住民からの信頼を得て、長期的に愛される施設を育てるための「攻め」の経営戦略でもあります。特に、清掃・管理体制の充実は、施設の品質を担保するだけでなく、近隣トラブルを未然に防ぎ、条例の趣旨を実践する上での要となります。
私たちインビックスは、箱根・熱海エリアの地理と法令、そして地域が求めるものを深く理解しています。単なる清掃サービスに留まらず、オーナー様が安心して事業を継続し、成長させていくためのパートナーとして、法令遵守の観点からもサポートを提供いたします。物件選びの段階から、ぜひお気軽にご相談ください。
民泊運営の「面倒」、丸ごとお任せください